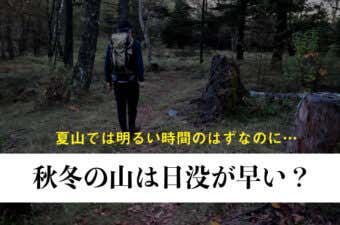山岳遭難の現場から ~Mountain Rescue File~ No.7
長野県警山岳安全対策課では、実際の遭難事例を掘り下げ、その原因や背景を検証しました。今回は、リスクに備えることの重要性ついて、事例を参考に考えてみましょう。
2024/09/11 更新
目次
山岳遭難事例から学ぶ、リスクに備えることの重要性
今年の夏山期間中、長野県内では116件の遭難が発生しました。滑落や転倒のほか疲労による行動不能遭難も多発し、死者行方不明者16人を含む125人の方が遭難しました。
偶発的な原因による遭難もある一方で、実力に見合ったルート選定やリスクを見越した適切な判断をしていれば防ぐことができた事例も数多く見られました。
登山は、荷物を担いで長時間歩き続けるという点では持久系スポーツの側面がありますが、単なるスポーツには分類しきれない特有の要素があります。
それは、登山が自然の中で行われる行為であるため、常に何らかのアクシデントに遭遇する可能性があり、リスクを適切に認識し、回避しながら行動することや万が一アクシデントに遭遇した際はダメージを最小限に留める等、常にリスクマネジメントが求められる活動であることです。
今回はこの夏に中央アルプスで発生した道迷い遭難を事例に、リスクに備えることの重要性について考えていきたいと思います。
中央アルプス・中岳にて、濃霧による道迷い遭難が発生。救助要請により遭対協が救助

出典:PIXTA(乗越浄土から見る天狗荘と中岳)
- 発生日
- 2024年7月24日
- 発生場所
- 中央アルプス 中岳
- 遭難者(Aさん)
- 51歳男性
- 概要
- 単独で登山中、道に迷い、行動不能 。自身で救助を要請し、中央アルプス地区山岳遭難防止対策協会の救助隊員に発見され、無事救出された。
初めての中央アルプス
Aさんは、愛知県在住の50代の男性で、登山歴は約3年。登山を始めたきっかけは、「何か運動を始めようと思い、登山であれば歳をとっても始められる」と考え、試しに地元の愛知県の本宮山(ほんぐうさん・東三河最高峰:標高800m)に行ったところ、自分の力で山頂にたどり着けたことに達成感を感じ、以来、山登りに魅力を感じるようになったそうです。
Aさんは、月に1回程度の頻度で愛知県近郊の山に登っており、長野県の山は過去に御嶽山にツアーで登ったことがあるそうで、中央アルプスは今回が初めてだったそうです。
木曽駒ヶ岳を選んだ理由は、自宅から車で行ける山域で、かつ日帰りが可能な登りやすそうな山だったことと、10年くらい前に駒ヶ岳ロープウェイで千畳敷まで行ったことがあり、その時に見た千畳敷カールのその先に行ってみたいと思ったこと、それに下山後の名物「ソースカツ丼」も決め手の一つだったそうです。
Aさんのこれまでの登山は、仕事仲間と複数人で行くことが殆どでしたが、今回は急に予定が空いたため、他に休みの都合がつく人がおらず、一人で木曽駒ヶ岳へ行くことにしました。
当日の朝、菅の台からバスに乗車し、駒ヶ岳ロープウェイを利用して千畳敷に到着しました。しかし、一帯は朝からかなり強い雨が降っており、居合わせた他の登山者も出発を見合わせるほどだったそうです。
Aさんも周囲の登山者の様子を見て出発を見合わせ、その後1時間ほど経過すると雨足が弱くなり、他の登山者が行動を始めたのを見てAさんも木曽駒ヶ岳を目指して行動を始めました。
濃霧の山頂に一人きり
行動を開始したものの雨は相変わらず降り続いており、その上、一帯は非常に濃い霧に包まれていました。途中の宝剣山荘のあたりまでは、他の登山者が複数いたものの、次第にその数も少なくなり、その先の頂上山荘の近くまでは4人家族のパーティーと隣り合うようにして登っていたそうですが、その4人も頂上山荘でトイレに寄るため別行動となりました。
Aさんは、その家族と別れる時に山頂の方向を教えてもらったので、一人で山頂を目指して登っていたところ、頂上から降りてきたという2人組のパーティーとすれ違いました。その際、「山頂に行ってもあなただけだよ」と言われたそうですが、Aさんは、「せっかくここまで来たんだし」と、2人組に教えてもらった山頂の方向に向かって進みました。
そうして辿りついた山頂には2人組の言葉どおり、他の登山者は誰もおらず、登ってくる人もいなかったので、Aさんは、すぐに下山を始めることにしました。この時点では怖いという気持ちはあまりなかったそうですが、一人のため若干、不安な気持ちだったそうです。
相変わらず濃いガスが立ちこめる中、Aさんは50m先の視界も利かない濃霧の中、正確な現在地や正しい進行方向を把握する術も無いまま、下山を開始します。
厳しい言い方をすれば、この日、周囲の登山者をあてにしながら他力本願でたどり着いた山頂で、Aさんは初めて自分の判断で行動をしなければならない状況に置かれてしまったのです。

登山者が連なる晴天時の千畳敷カール
夏から秋の千畳敷カールは、晴天時であれば、多くの登山者で溢れ、登山者の列がコース上に連なるように続いており、たとえ地図がなくてもまず道に迷うことはないと言ってもいいでしょう。
木曽駒ヶ岳から中岳を経て千畳敷カールへの降り口となる乗越浄土に至るコースも、途中の中岳の通過にわずかなアップダウンがあるだけで、平坦な登山道が続きます。そのため登山初心者にも歩きやすく、ロープウェイによるアクセスの良さも相まって、人気があるのですが、裏を返せば、このような特徴に乏しい平坦な地形は、視界不良時は道迷いに陥りやすいという危険性があります。
記憶にない水流の出現
Aさんは、山頂から記憶をたよりに下山をしますが、中岳の巻き道付近で千畳敷カールへの降り口を誤信し、木曽側の急斜面に入り込んでしまいました。当初Aさんに道を外れたという認識はなく、他に登ってくる登山者を見かけなかったことに焦りを感じながらも、「下りきればロープウェイ駅に着くはずだ」と思い込んで足場の悪い斜面を下り続けてしまったのです。

Aさんが道を誤ったと思われる中岳の巻き道
しかし、次第に周囲が沢状の地形になり、沢の中に水流が現れたのを目にして初めて道を間違えたことを自覚したそうです。この時の状況をAさんは「なぜ、駅に向かっていると思い込んでいたのか自分でもわからないが、一人で不安な気持ちが恐怖に変わってきており、冷静ではなかったかもしれない」と振り返っています。
Aさんは自力で引き返すことはできないと判断し、午前11時頃、救助要請をするために119番通報をしました。Aさんの通報は、岐阜県の消防本部に入電し、岐阜県の消防本部が聴取した内容から現場が長野県の木曽駒ヶ岳であることが推定されたため、岐阜県の消防本部から木曽広域消防本部に事案が引き継がれ、木曽広域消防本部から管轄の警察署にも情報共有がなされました。
119番通報入電時の内容は「中岳付近で道に迷った」という程度で、携帯電話の電波状態が悪く、詳細は聴取できない状況でした。その後何度か電話のやりとりを続け、警察署からAさんに110番通報をするよう指示をし、11時30分頃、Aさんからの110番通報により、現場の位置が特定されました。
現場は、稜線の登山道から木曽側へ標高差にして150mほど下部の斜面であることがわかり、警察署ではAさんの捜索のため、付近の山小屋へ出動を要請することとしました。

木曽駒ヶ岳周辺には複数の山小屋が点在していますが、その中の一つの宝剣山荘に勤務しながら、中央アルプス地区山岳遭難防止対策協会(以下の「遭対協」と略)の救助隊員でもあるBさんが出動し、Aさんと合流すべく活動しますが、一帯は相変わらずの濃霧のため、3時間ほど捜索をしましたが発見することができませんでした。
110番画像通報システムを使って
日没が迫る中、午後5時頃、再度、警察署にAさんから「特徴的な大岩の下に移動した」との連絡が入りました。
Aさんは、警察署から通報した場所にとどまるよう指示をされていましたが、電波状態が悪く通話も途切れ途切れだったため「見つけて救助してもらえるのか」という不安と、動かずにじっとしているとあまりの寒さに耐えきれなくなり「このままでは死んでしまうかもしれない」という恐怖から、自力で斜面を登り返していたのです。
Aさんから連絡を受けた警察署では、近年導入された110番映像通報システムを活用し、Aさんから「特徴的な大岩」の画像を送信してもらいました。送られてきた画像には、塔のような形状をした「特徴的な大岩」が写っていました。

Aさんから送られた「特徴的な大岩」の画像
その日、宝剣山荘には、Bさんと同じく遭対協救助隊に所属し、班長でもあるCさんがガイド登山のため滞在していました。登山ガイドとして周辺の地形を熟知するCさんは、「塔の形状をした特徴的な大岩」の話を聞き、心当たりがあったことから、同じく遭対協救助隊員で雷鳥調査のために山荘に居合わせたDさんとともに、再度Aさんの捜索を行うこととしました。
Aさんは、運良く岩小屋のような場所を見つけましたが、立ち止まると体が冷えてきて本当に寒く、日が暮れ始めたときはライトもなかったので真っ暗の中、着の身着のままでの野宿を覚悟しました。
すると、遠くで人の声が聞こえた気がしたので、必死に何度も叫んでいたところ、声が近づいてくる感じがしたので、とにかく大声を出し続けて自分の居場所を知らせました。
やがて遭対協のC班長、D隊員の姿が見えた時のことを、Aさんは「涙があふれてきて、感謝の気持ちしかなかった」と振り返っています。それだけ不安と恐怖の中で救助を待っていたのでしょう。
捜索開始から約1時間後、Aさんは無事発見され、19時半頃には宝剣山荘にたどり着き、その日は宝剣山荘に宿泊し、翌朝、無事下山することができました。
日帰り予定とはいうものの……
発見時、Aさんは雨のためずぶ濡れで、日帰り予定を理由にヘッドライトやビバーク装備を携行していませんでした。
今回は、偶然、現場をよく知る遭対協班長のCさん達が近くの山荘に滞在していたため、当日中に発見され解決となりましたが、Cさん達がいなければ、Aさんは現場で厳しいビバークに耐えなければならなかったかもしれませんし、仮にビバークとなれば、乏しい装備では命に関わる深刻な低体温症に陥っていたかもしれません。
ビバーク装備の携行については、これまでも度々、言及していますが、予期せぬアクシデントに備え、最低限、簡易シェルター、防寒着、ヘッドライト、非常食の携行をしていただきたいと思います。
特にこれから秋が深まると山の寒さは厳しさを増します。加温や保温ができるものやバーナーなど熱源となるものの携行も検討していただきたいと思います。
雨と濃霧の中、ガイドブックは開けず……
Aさんは、これまで登山では、登山地図アプリのヤマップを使っていたそうですが、今回は事前に地図をダウンロードし忘れてしまい、遭難当日に山中で使用を試みましたが、電波状態が悪く、地図が表示されないため、使用できなかったそうです。

濡れてしまったガイドブック
登山地図アプリの多くは、事前にスマートフォンに地図データをダウンロードし、スマートフォンのGPS機能を用いて、読み込んだ地図上にナビゲーションのように現在地が表示されるという仕組みになっています。
ですから、通信環境の悪い山中でいきなり地図アプリを使おうとしても、今回のAさんのように容量の大きな地図データの取り込みができなければ使用できない場合があります。
地図アプリは、道迷い防止に非常に有効ですが、事前にその特性、使い方をしっかりとマスターし、バッテリー対策を講じた上で利用すべきでしょう。
Aさんは地図アプリのほか、普段から登山に際し、該当山域のガイドブックを携帯して登山をしているそうで、今回もガイドブックを持って入山ました。
しかし、当日は雨足が強く、とても行動中にガイドブックを取り出して開けるような状況ではなかったそうです。
そのため、土地勘のないAさんは、前述のとおり、登山中は進行方向を逐一、他の登山者に聞きながら行動していたそうです。救助後に見せてもらったガイドブックは、雨に濡れて肝心の地図ページは破れて使えなくなってしまいました。
紙媒体の情報は、スマートフォンの紛失、故障、地図アプリの不具合などのトラブルの際のバックアップにもなりますので、併用をお勧めしますが、携帯性を考えるとガイドブックではなく、登山用の地図が良いでしょう。地図専用の防水パック等を活用すれば雨天でも使用することができます。
濃霧の行動のリスク
今回の遭難の直接的な要因は、当日の悪天候、特に「濃霧」です。


2枚の画像は、今回の現場近くに立つ宝剣山荘の近くで撮影したものです。濃霧の立ちこめる画像は、翌日Aさんと同行下山した際に撮影したものです。うっすらと見える建物との距離は約50m程度で、この日も朝から濃霧が立ちこめ非常に視界が悪い状況でしたが、Aさんが道に迷った前日はもっと視界が悪かったそうです。
このような濃霧の中、今回のAさんのように初めてのコースを一人で下山しなければならないとしたら、相当の不安を覚えるのではないかと思います。心理的な余裕を失い、冷静な判断ができなくなれば、ますます道迷いのリスクが高くなります。
Aさんが遭難した日は同じ中央アルプスの檜尾岳でも70歳代の女性が同じように濃霧の中を下山中、道を見失い救助されています。それだけ道迷いのリスクの高い気象条件だったと言えるでしょう。
もう一枚の青空が映える画像は後日天候の良い日のパトロール時に撮影したものですが、同じ場所でも受ける印象は全く違います。
気象条件は登山の安全を左右する重要な要素です。ただ、いつも晴天の登山ばかりでは、いざ悪天候に見舞われた時に対応できなくなってしまいますし、行動中に天候の悪化に見舞われることもあるでしょう。
長く登山を続けるのであれば一定程度の悪天候時の行動経験も必要です。道迷いや低体温症などの悪天候時のリスクを認識し、対応できる備えを持った上で入山してもらいたいと思います。
まとめ|今回の事例から見えた、リスクに備えることの重要性
◆道迷い防止のために
・周囲の登山者をあてにしながら他力本願で登山するのではなく、自身の判断で行動できるよう、登る山やルートの状況確認をはじめとした事前準備を入念に行なう
・登山地図アプリは道迷い防止に非常に有効だが、その多くは通信環境のよい場所で事前にスマートフォンに地図データをダウンロードしておく必要がある。そうした特性や使い方をしっかりとマスターし、バッテリー対策を講じた上で利用する
・スマートフォンの紛失、故障、地図アプリの不具合などのトラブルの際のバックアップとして、登山用の地図を携行する。防水パック等を活用し、雨天時の濡れ対策もしておく
◆予期せぬアクシデントに備えて
・乏しい装備では、命に関わる深刻な低体温症に陥るリスクが高まる。日帰り予定であっても最低限、簡易シェルター、防寒着、ヘッドライト、非常食を携行する。加温や保温ができるものやバーナーなど熱源となるものも携行するとなおよい
終わりに
夏山が終わり、9月に入るとアルプス等の高山では徐々に紅葉が進み、日増しに秋の気配が色濃くなります。日照時間も短くなり朝晩の冷え込みも段々と強くなりますので、ヘッドライトや防寒具、暖をとれるバーナーや保温ボトルなど装備を整え、入山をしていただきたいと思います。近郊の里山に日帰り予定で登る場合も、いざという時に備えて前述したような緊急時対策装備は削ることなく携行をお願いします。
また、秋の晴天時は快適な登山が期待できますが、10月以降は、標高の高い山域では低気圧や寒冷前線が通過する際は、みぞれや吹雪となる場合もあります。
登山の際は必ず事前の気象情報を確認して行動に支障が出るような悪天候が予想される場合は、入山を見合わせるなど安全を優先した判断をお願いします。
短くも魅力的な秋山シーズンを安全に楽しんでいただきたいと思います。