こんにちは。私も混ぜてください。
既出の回答と多少重なるところもあります。
まず初めに,(回答No.11)
>PCといういいかたはNECが発信元でしょうか?パソコン=PC,賛否は分かれるでしょう。これも日本だけしか通用しないと聞きます。
イギリスやアメリカ,韓国などの人の書いた文章にもPCという略語はごく普通にでてきます。むしろ,日本でしか通じないのは「パソコン」という呼び方ではないでしょうか。
発信元はNECよりもIBMのような気がします。(以上,自信ナシ)
で,本題。私なりに推測をまじえて回答しますと,
Q1.なぜ「ホームページ」の略として「HP」という言葉が使用されているのでしょうか。
A1-1.homeの頭文字がhで,pageの頭文字がpだから,両者をつなげたのです。…という意味の質問ではないですよね。(^^)
おそらく,日本ではよく使われる単語だから短く縮めたのではないでしょうか。
英語圏を始めとして,よその国ではホームページを本来の意味で用いているので,わざわざそのページについてのみ言及することはあまりないと考えられます。
また,webpageというさほど長くない1語で表せるので,あえてwpなどと略す必要もないのでしょう。
(外国語の文章の中では特に長くなくても,日本語の文章の中でそのまま外来語としてカタカナで書くと長く感じられるので,いろいろと省略形が生まれるのだと思います)
A1-2.また,「なぜヒューレットパッカードを意味していたにもかかわらず,別の意味の略語が持ちこまれたのか」という点では,使う人の数の問題もあるでしょう。
日本で「ホームページ」という単語を知っている人は非常に多いでしょう(コンピュータと縁のない人でも言葉ぐらいは知っているかもしれません)。
Hewlett Packard社を知っている人はそれに比べると少なく,おそらくコンピュータを実際に使っているか,使っていなくてもそこそこ関心のある人がほとんどでしょう。
そして,そういう人の中でも「HPといったら同社のことに決まっているじゃないか」という意識の人はさらに少なくなるのだろうと思います。
まだ世の中にパソコンというものが生まれて間もない頃(当時はマイコンと言った),関数電卓といったらTI(テキサス・インスツルメンツ)かHPか,という感じだった時代を知っている人(私とか…)にとっては,確かにHPをホームページの略として使われると,ちょっと待って,という感覚があります。
しかし,homepageという単語を略すとそうなってしまう以上,しかたがないのかなという気もします。つまり,ホームページという単語の誤用を元から正さない限り,HPという略語も広く使われつづけるのでしょう。
考えてみると,略語の意味が複数になるというのはHPに限った話ではなく,ブランドに関心のある人ならCDといったら「クリスチャン・ディオール」に決まってる,というでしょうし,金融関係者なら現金の支払いはできるけれど預け入れができない機械を連想するでしょうし,また株などに投資している人なら転換社債のことと思うかもしれません。
ただ,これらはそれぞれの意味で使われるときの文脈がかなり離れているので,そこに「コンパクト・ディスク」という新しいモノが生まれて,同じCDという略語が使われ出しても,あまり混乱しなかったのでしょう。
それに対して,ヒューレット・パッカードとホームページはどちらもコンピュータ関係という似通った文脈で使われるので,前の意味を知っている人には抵抗を感じやすいといえるでしょう。
Q2.また[なぜ]「Webページ」または「Webサイト」の意味で「ホームページ」という言葉が誤用されているのでしょうか。
新聞やTVなどのマスコミが誤用を広めたのでしょうか。
A2.程度の大小はさておき,マスコミの影響はあるでしょうね。
まだ個人対象のプロバイダが生まれるか生まれないかという頃(7~8年ぐらい前?),会社がウェブページを作るとそれだけで新聞の経済面に(新商品の発売のように)記事となって載っていた時代がありました。
会社側は,「これが弊社のホームページです」といって,まずは表紙とでも言うべき,一連のページのトップの画面やURLを紹介したのでしょう。
作った人の意識としては,まさにそのページだけがホームページであって,そこから先に会社の概要や商品の紹介などの各ページがある,と考えているのでしょうが,記者のほうは「なるほど,こうやってインターネット上で情報を公開するものをホームページというんだな」と受取って,そういう紹介の仕方をしてしまう。
あるいは,記者が勘違いしていなくても,記事を読んだ人が,トップページの写真の下に「なんとか社のホームページ」と書いてあるのを見て,そういう風に誤解した,ということもあるでしょう。
そのうち,「ホームページを作ろう」なんていう雑誌の記事や,単行本や,テレビの講座などが出てくれば,初めて聞いた人は,そういうものなんだと思ってしまうのも無理からぬことでしょう。
もともとhomeという英単語は,家庭のことですから,「そこをベースにしてあちこち出かけるけれど,いずれ戻ってくるところ」という発想から,「基点」「本拠地」などの意味が派生したのでしょう。
したがって,第一義(ブラウザを起動したときのページ)や,いわゆるトップページの意味で,ホームページというのは,この意味からして理にかなっているわけです。(前者は,自分がそこを基点にしてブラウジングを行なう。後者は,うちのページを見にきた人に,そこを基点にしてブラウジングをしてもらう。)
ですが,すべてのウェブページをホームページと呼んでしまうと,ホームの意味はどこへ?となってしまうわけです。
野球のホームベース,ホームグラウンドといった言葉を正しく使っている人が,ホームページとなると「ホーム」の意味を忘れてしまうというのも面白いものです。(まあ所詮は外国語だから,ですかね。)
「4つのベースを順次踏んで回ると得点になる」というべきところを,「4つのホームベースを…」と言っているようなものなんですけれどね。
No.9:
>他の業界にも、おそらく略せば HP になる言葉はあるでしょう
たとえば,仕事率の単位として「馬力」(HorsePower)をHPと略すことがあります(今はSI単位のワット Wが多いかな)。これは英語圏でも使われている(いた)はず。
No.13:
>ことあるごとに「HPとはヒューレット・パッカードだ」「ホームページという言葉の使い方は誤っている」と
>少しずつでも主張していくほかないと思います。
そうですね。私もコンピュータ関係の授業をするときはこんな言葉に関する話をしているのですが,ただ一般の人と話をするときには相手に合わせてしまって「ホームページ」などと言ってしまうことが多いです。
No.5の回答にもあったように,かつてはPDSとフリーソフトとの区別が広まって定着したという実績?もあったのですが,ホームページやハッカーなどのように,これだけ広まってしまうと,なかなか難しそうです。
筑波大学の久野さんという人が,「ホームページ」という言葉がどのような意味で使われているかを集めて分類しています。
だんだん増えてきて,最新版では28種類もあります。
これを見ていると,ウェブページ一般の意味で使っているのなど,まだかわいい?ほうで,とんでもない意味で使われている場合もあることが分かります。
『恋のダンスサイト』の歌詞もきちんと入っているのはさすがだなと思いました。
うまくまとまりませんが,長くなったのでこのへんで失礼します。











![その他([技術者向] コンピューター) イメージ](https://gazo.okwave.jp/okwave/images/related_qa/c205_4_thumbnail_img_sm.png)
![その他([技術者向] コンピューター) イメージ](https://gazo.okwave.jp/okwave/images/related_qa/c205_3_thumbnail_img_sm.png)












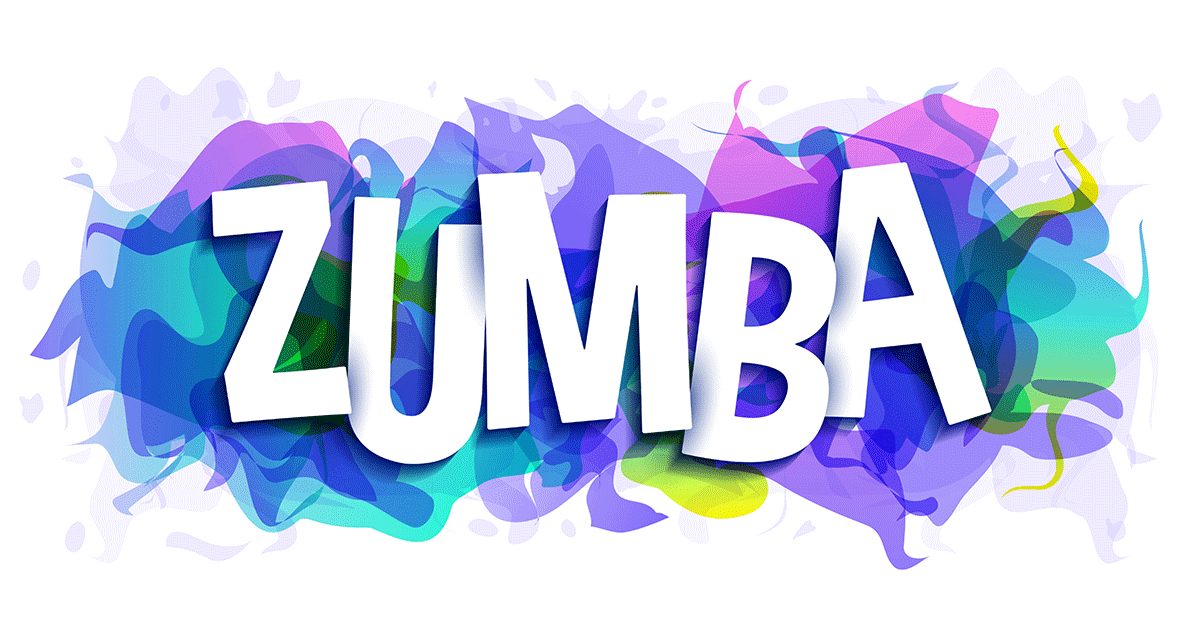









お礼
ご回答ありがとうございます。 遅くなってすみません。 この質問に類似した内容のページがあったのですね。