イソップ物語は国によってその民族の価値観とその国に生息する動物や昆虫によって話が作り変えられているようです。日本では仏教の教えや儒教の教えに合うように結末が変えられています。(日本のイソップ物語は優しい思いやりのある主人公が登場します)
世界中に住む蟻は変わりませんが蟻と比較される甲虫(原作)は国によって変更せざるを得なかったようです。日本ではキリギリスですが、英語版ではgrasshopperとなっています。Grasshopperとはバッター、イナゴ、キリギリス類の総称です。岩波文庫「イソップ寓話集」では甲虫(糞を集めて卵を産みつける)が怠け者になっています。僅か7行の短い話です。結論も将来のことを考えないと時節が変わったときにひどく不幸な目にあうものです、とだけで食べ物を分けてあげたかどうかには触れていません。
一方英語版の最後は、各話が必ず短い教訓で終わります。「夏に音楽を奏でて忙しかったのなら、今度は踊ったらどうだ。こう言って蟻たちはキリギリスに背を向けて仕事に戻って行った。人生には働く時と楽しむ時があるのだ。」
日本語版(ギリシャ語版の翻訳)も英語版も我々が読まされてきた話と若干違いますが、キリギリスが褒められてはいません。私の理解ではキリギリスが褒められたのではなく、イソップ物語の前編に流れるのは古代ギリシャの奴隷たち(我々の知っている近代の奴隷とはだいぶ異なりますが)の人生訓、処世術であり、当時の物語が現代の人間にそのまま教訓にならない場合もあるということです。しかし、世界にはキリギリスの生き方を善しとする民族もいるのでしょうね。
日本人が日本人向けに書き直した蟻とキリギリスは、蟻は働くこととの意義を説いた後にキリギリスに食べ物を分けてあげ、キリギリスは有難うとお礼を言って立ち去ることになっています。これは仏教の教えです。

























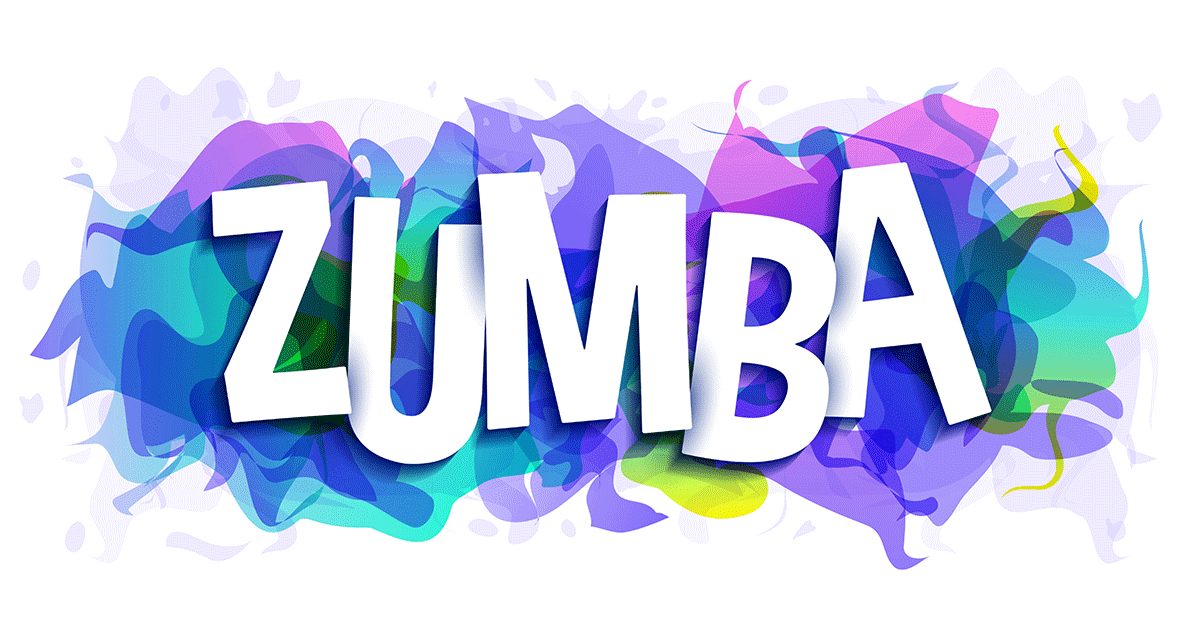









お礼
大変詳細なご回答ありがとうございます。お陰様でおおむね見えてきた気がします。私が昔目にした一文は、フランスの大臣でしたか、「日本人はウサギ小屋に住む働き中毒」とか言われた頃、そんな流れの中で、労働観の違いを説明する上での、多少ご都合主義の物だったのかもしれません。