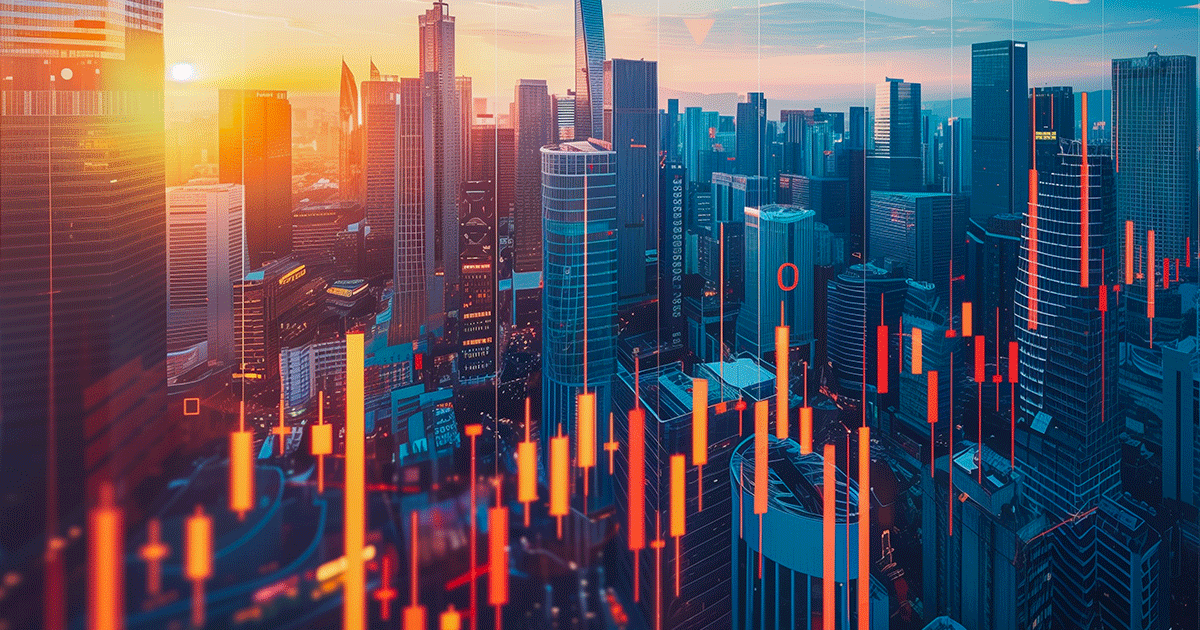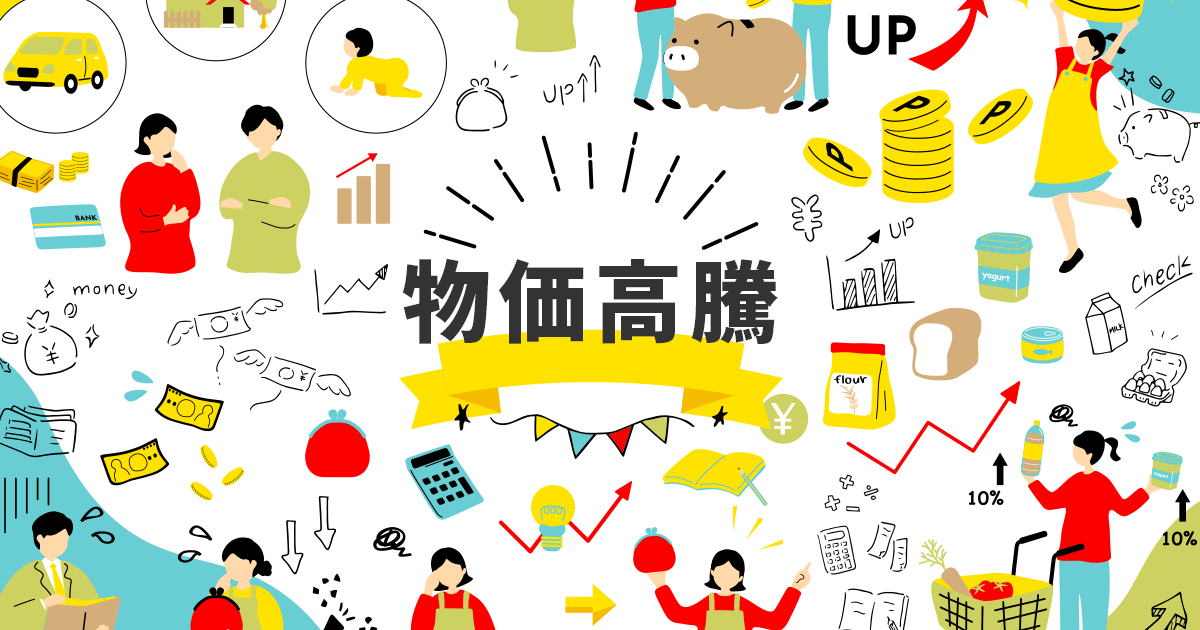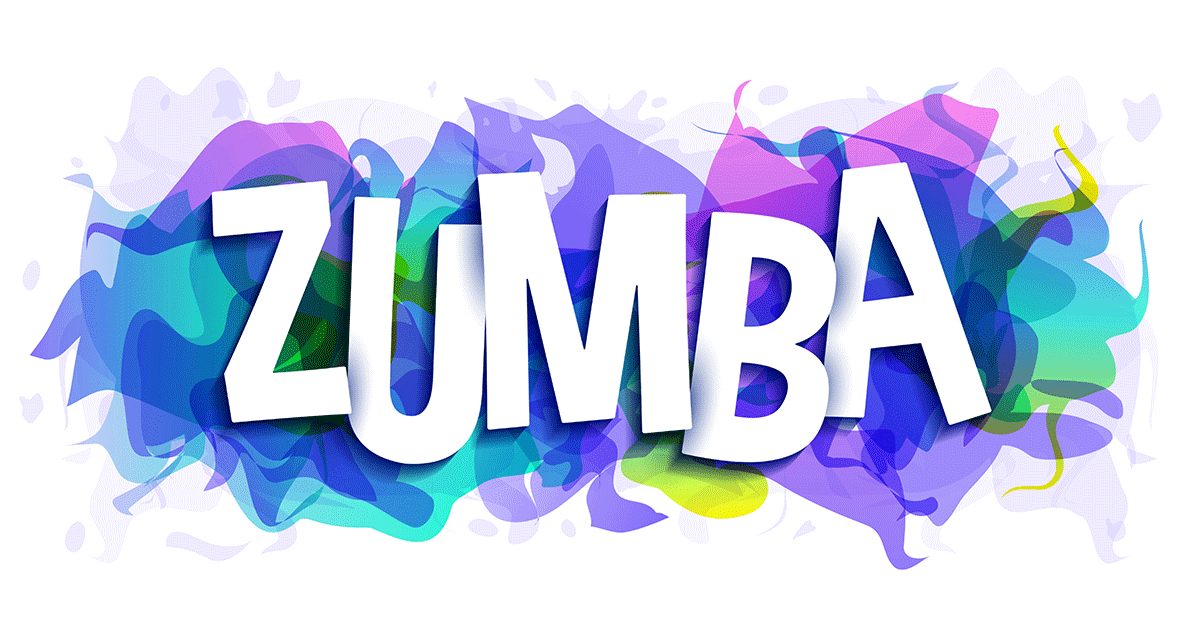簿記
- 経常利益とか純利益とか利益について教えてください
以下の場合、この会社の利益というのは、会計上、何利益になるのでしょうか。経常利益とか純利益とか・・・。ご専門の方、ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。 「組合の要求書で「200円以上の時給アップ」と掲げたが、簡単にいうと、今年度の会社の利益が1億円あたりで着地するとのこと。またこの利益の一部を設備投資に回したいとのこと。その利益の中でアルバイトの皆さんににどれだけ還元できるかというと時給30円が限界とのこと。30円×8時間×1ヶ月のアルバイトの方の平均稼働日数15日×全店舗400人分で単純計算1,440万円になるとのこと。よって、この4月からは30円アップが会社としては限度。」
- 受付中
- 簿記
- ichiichi0517n
- 回答数1
- 建設業経理事務士3級について。
取り立て依頼中の約束手形の期日到来した時の 勘定科目を教えてください。 支払手形の期日到来につき当座から引き落としの仕訳を教えてください。 よろしくお願いします🙇
- 簿記 資本金の記帳方法について
当期純利益 10000 円を資本金勘定に振りかえた。 損益 10000 資本金 10000 理解することができないのです。 ご指導をよろしくお願いいたします。
- 簿記 手形貸付金について
下記の意味が理解できないのです。 B社は、A社からの融資の申し入れを受け、A社振出し、当店 宛の約束手形10,000円と引き換えに同額の小切手を振出した。 約束手形と引き換えに 同額の小切手を振り出したとはどういう意味でしょうか。 よろしくお願い致します。
- 会計(弥生会計)の決算書の操作
簿記の初心者です。 どなたか、教えてください。 弥生会計会計ソフトを使っています。不慣れな仕分け、伝票の振替等が終わり、決算書を出そうとすると、「損益計算書の決算額と内訳金額の合計が一致していません」と表示され、二つの科目と決算額が表示されます。 (販売金額と雇入費です) 内訳金額の合計とはどういう意味なんでしょうか? どこをどう見て、一致させればいいのでしょうか? どなたか、教えてくださいませ。 よろしくお願いします。 コメント
- ベストアンサー
- 簿記
- XJR400nori
- 回答数1
- 建設業経理事務士3級 問題について
下記の問題について ご指導よろしくお願いします。 借入金に対する利息 支払額 12000円のうち 6400円は次期分である。 解答は (借)前払利息 6400 (貸)支払利息 6400 よろしくお願いいたします。
- 回収サービス業務費について
金融資産について勉強しているのですが、その中の債権回収サービスについて、「通常得べかりし収益」と「実際の回収サービス業務費」との差額を考える話が出てきます。 ただ、ググッてみても 「通常得べかりし収益」が何を意味するのか、 なんで「実際の回収サービス業務費」とで差額が発生するのか良く分かりません。 このあたり詳しくご教授頂きたいですm(_ _)m
- 締切済み
- 簿記
- Lifeislikehell4
- 回答数1
- 減価償却累計額について
減価償却 の 間接法について学んでいます。 間接法の貸借対照表の作成をするなかで 下記が減価償却累計額の説明 なのですが 理解ができませんのでご説明お願いします。 減価償却累計額は資産のマイナスを表す 勘定科目なので仕分けの際は 通常の資産の勘定科目とは逆で増えたら右 借方 減ったら左 貸方に仕分けし 貸借対照表に載せた時には 資産の金額をマイナスしていきます。
- 建設業簿記3級 減価償却について
建設業簿記3級の減価償却について教えてください。 直接法と間接法の2つの方法がありますが 3級の試験では 間接法 が範囲とされていますが テキストには 直接法の説明も詳しくされています。 3級の試験を受けるのですが直接法についてもきちんと理解しておくべきでしょうか?
- 日商簿記3級の問題について
問題文が下記です。 従業員に建て替えていた 5000円と所得税の源泉徴収分 4500円と社会保険料 17,000円を差し引き とあります。 所得税の源泉徴収分 とありますが 所得税 4500円分 所得税の源泉徴収 4500円分 違いを教えてください。 よろしくお願いいたします。
- 回収業務資産の時価とは
簿記1級の金融商品会計のテキストに回収業務資産の時価とあったのですが、 回収業務資産自体は債権の取り立てを行うサービスと理解していますが、回収業務資産の時価というのが何を言っているのか分かりません。 このあたりご教授頂きたいです
- 締切済み
- 簿記
- camelandy123
- 回答数1
- 日商簿記 仮受金について
下記、問題について ご指導ください。 先日 仮受金として処理していた1万円は売掛金に対するものであるという連絡を得意先から受けた。 仮受金の内容が判明したので 仮受金が借方になるのはわかるのですが、売掛金に対する入金であったのがわかったことでなぜ 貸方になるのでしょうか。よろしくお願いします。
- 金銭債権・債務に対する償却原価法
金銭債権・債務に償却原価法を適用する場合についてなのですが、 金銭債権・債務の場合、 ・9200千円の商品に対して10,000千円の手形を渡した ・8500千円の売掛金に対して10,000千円の手形を渡した などが償却原価法を適用する例で挙げられています。 額面との差額があれば社債と同様に償却原価法を適用するというのは感覚的に理解してますが、 そもそも同額(9200千円や8500千円)の手形って用意出来ないのでしょうか? 普段の買い物で2300円の商品を購入したが5000円札しかなかったみたいなイメージ的になるのでしょうか? 社債の場合は買い手の購買意欲を高めるために差額(割引発行など)が生じるケースがありますが、金銭債権・債務の場合はまた目的というか差額が生じる要因が異なりますよね?
- 締切済み
- 簿記
- camelandy123
- 回答数1
- 簿記2級の仕訳
材料や製品の棚卸減耗損が出た場合、仕訳で棚卸減耗損を経由する場合と、製造間接費や売上原価に直接振替える場合が有ります。 棚卸減耗損 50 / 材料 50 製造間接費 50 / 棚卸減耗損 50 製造間接費 50 / 材料 50 テキストでは、どちらの方法もOKの様なのニュアンスが感じられます。 しかしながら、退職給付費用や賃金は、1行の仕訳にするのはオカシイ感じがします。 退職給付費用 50 / 退職給付引当金 50 製造間接費 50 / 退職給付費用 50 ×製造間接費 50 / 退職給付引当金 50 賃金 50 / 現金 50 仕掛品 50 / 賃金50 ×仕掛品 50 / 現金 50 私の現在の考えでは、賃金・退職給付費用は2行の仕訳。棚卸減耗損は1行でも2行でもOK。 この辺りはどの様に、考えれば良いでしょうか?
- 原価ボックス 日商簿記2級
原価ボックス先入先出法 4/18 3000円×50個 3000円×150個 3200円×200個 3300円×20個の説明をしてください お願いします
- 締切済み
- 簿記
- daize123A-
- 回答数1
- 個人事業主の仕訳表について
個人事業主には、事業主借という勘定科目があるともいます。何か物を買たとき、事業主の財布から出して購入したときに使うものかと思います。言い換えれば、すべての経費は事業主からの財布から出して購入したものだから、物やサービスに支払った経費の貸方勘定科目はすべて事業主借としてよいのでしょうか? 事業主(すなわち自分)は、どこで購入したかはレシートや領収書はすべて残していることを前提で教えていただければと思います。
- 簿記2級の仕訳回答方法に関して
閲覧ありがとうございます 簿記2級の勉強の際に仕訳の回答で困っています 簿記3級では同一の勘定科目は同仕訳内では1度のみの使用で 貸方借方内で複数回使わずに合算しました しかし簿記2級の学習をしていると貸方と借方で合算しないパターンが大変多く見受けられ何が正解なのかわかりません 大手のテキストでも同一勘定科目を合算せず解説していますが、大手動画投稿者の解説動画では合算していたりとよくわかりません 実際の試験での正しい回答方法を知っている人がいたら教えてください 例 建物 1200 / 現金 1200 固定資産圧縮損 600 / 建物 600 建物勘定を借方600にしないのは何故? その他有価証券 40000 / その他有価証券評価差額金 24000 / 繰延税金負債 16000 動画だと上記仕訳ですが スッキリわかるテキストだと貸方評価差額金が40000で借方に評価差額金16000が計上され合算されていない などです
- 簿記2級の退職給付費用に付いて
退職金が「退職給付引当金」を超過していた場合、不足分は「退職給付費用」「退職金」のどちらの勘定科目を使うべきですか? それとも、簿記2級では、「退職給付引当金」が不足する事は、論点には想定されていませんか?