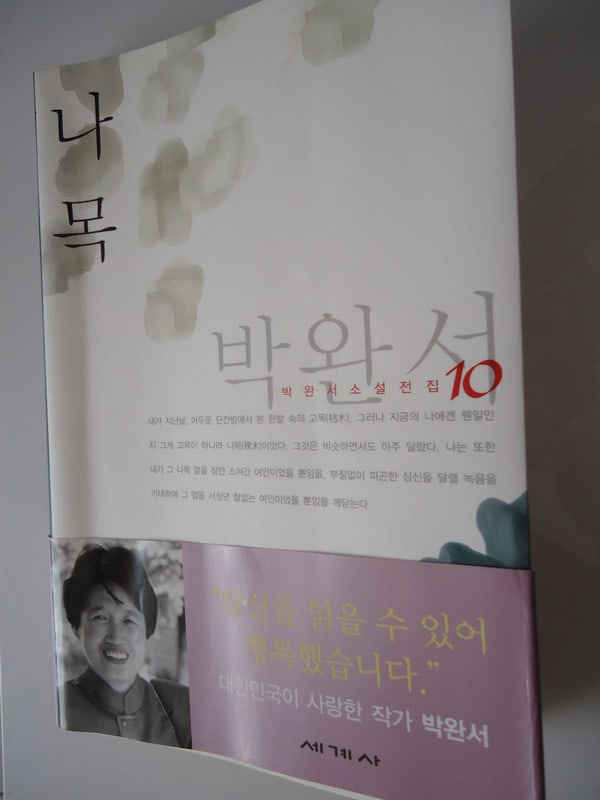翻訳 朴ワンソの「裸木」62
214頁~218頁
14
父の死を悲しいこととしてさほど思い出さないことは異常なことだ。私は父の愛をほとんど独占していた。父の死が突然訪れた時も、彼の死よりはその頃に経験した大学入試の不合格がひときわ衝撃的なこととして思い出された。もちろん、一人の家長の死と一人の女の子の大学入試の失敗なんかは、比べられることではないけれど、父の死は兄達と一緒に経験できて、大学入試の失敗は私だけのことなので、そういうふうに思い出されるのかもしれない。
いずれにせよ、喪中の当時も絶対に憂鬱な雰囲気ではなかったような気がする。オキ兄もヒョキ兄も一度さんざん身をよじって泣いてからは、すぐに悲しみから回復していった。喪中の当時よりは、49日の法要を執り行う時の、ひときわひりひりと突き刺さるような悲しみが今も生々しい。
肌がばら色で美しく、耳目口鼻が整ってあでやかな若い尼僧の泣き声が、本堂に朗々と響いた。
―父母は私を育てる折にどんな祈りを込めたのだろうか。ぬかるんだ場所は母が横たわって、乾いた場所は赤ちゃんを寝かせて、食べ物でも味を見て、とても苦いものは母が食べて、甘ったるいものは赤ちゃんが食べて。-
本堂の庭にはキンセンカや松葉牡丹、桃が真っ盛りだった。だしぬけに砲声が殷々と聞こえた。
母はお釈迦様の前にきちんと新しい紙幣を置いて、心を込めてお辞儀をしきりに繰り返した。
母の表情は静かながらも侵すことのできないほど厳粛だった。万寿香(線香)が青い煙を出し続けて、泣き声は朗々と続いた。
砲声がまた殷々と聞こえた。しかし本堂の内外は太古のごとく静まり返っていた。キンセンカの魅力的な花がぼやけて見えて、鼻筋がずきずきするのは、今更のように父の死が悲しくてということではなかった。
泣き声は非常に悲しくて、尼僧の声があまりにも子供っぽく朗々として胸が痛んだ。
母もハンカチで涙をぬぐった。悲痛な姿でずっと黙々と立っていた兄達も喪服の袖の中からハンカチを取り出して目を押さえた。
泣き声は非常に悲しかった。
―人間70は古来稀なりです、80長生き、90春光。将来100歳を生きるとしても、病気の日と寝ている日があって心配気がかりをすべて除いたら、たった40を生きられない初老のような私達の人生、あっ、一度死んだら芽が出るのかずっと日ごとに限りなく悲しい。命40に該当する花は散るのを悲しむな。-
しかし、49日法要から戻る道は楽しかった。兄達はよく口にしていた愉快な冗談はもちろん、喪中だったけれど喪服を脱いで紳士服に着替えて、成人の俊秀な青年であることを誇示しながら、まだ少しぼうっと悲しみに浸っている母を、両方で優しく脇をかかえて歩かせていた。母はそんな手助けにこのうえなく満足しているようだった。
「もう少しだけ生きていたら。嫁をとること、婿をとること、みんな慶事だけ残してしまって。欲もあまりない主人が」
母は、母屋の板の間で49日の法要の食事で食器を配りながら、ふうと言った。
「お母さん、今はもうお父さんのことを考えるのは止めて、お母さんも長く生きてください。お父さんの分まで長く長く生きなければ」
ウキ兄が母の膝を揺すりながら甘えるように言った。
「そうですよ。本当にお母さん、嫁を見るんですよ。孫も見なければ。孫の嫁は見られないですよ。こんなに若いですから長く生きてください」
ヒョキ兄が母の頬に自分の頬を当てた。
「えーい、いやらしい。もう大きいのに…」
母は初めて明るく笑った。綺麗な顔だった。父が亡くなってからは油を塗らないで、やや平たくなった頭が立ってみえたが、それでも自然の艶を保った黒い頭をきれいに櫛を入れて、きれいな輪郭の顔と美しい歯も前と同じだった。
私は母があまりにも好きだった。しかし、私がしたい話を兄達が全部してしまって、甘えたりするので、私はもう一度繰り返ししても照れくさいので黙っていた。少しわびしかった。いつも父は私の物で、母は兄達のものだったが、父がいない今、母を兄達と分かち合いたかったが、兄達はそんな私の素振りにあまりにも思いやりがなかった。
砲声がまた聞こえた。今はっきり聞こえてまた聞こえた。遠いけれど、ぱんぱんと続けて聞こえた。しかし、誰も不安がらなかった。
二百坪近い大地に引きこもった風雅な古家は本堂の中よりもっと静まり返っていた。
裏庭には二度目に咲いた四季咲きの薔薇の葉が一、二枚落ちていた。
翌日は少し違った。砲声が至近距離に聞こえて、大通りには避難民が溢れているそうだ。しかし家は大通りから奥まっていて、避難民を実際に見られなかった。
伯父が何回もやってきて、兄の友達がせわしなく行き来した。黄昏の時分になるや伯父の顔色が少し悪くなり、母と長く何か相談している様子だった。息子達だけ避難させることで合意した様子だった。分家本家の息子達は全員で四名だが、本家のチンイ兄さんは国軍将校なので家にいるはずもなく、実はそのために本家では慌しく余裕がなく焦っているように見えた。
もち米で麦こがしを作り、海苔巻を包み、おかずを用意し、母は奔走した。私も母を助け、兄達の下着を用意してリュックサックを繕った。巨大な避難の荷物が三つできたのは、かなり暗くなってからだった。
兄達はまだ戦争を実感していないようだった。登山にでも出かけるように、ちょっと騒々しく家を出た。
暗いのに、不安で心配して外に出ている町内の人達にまで余裕のある冗談を交えて挨拶し、路地の入口の小さな雑貨屋から間食の材料を買って避難の荷物に追加するなど、幼稚な振る舞いをしながら出発した。
結局は、こんな広告紙のようにいろいろな人々に見られて出発したことが、後日いろいろな面で助けになった。
彼らは翌日の早朝に戻ってきたからだ。彼らは前夜にあまりにもたくさんの友達の家に立ち寄り、挨拶して一緒に行く友達に協力していたために、そのまま漢江を渡れなかったのだ。
幸いにも戻る時は誰の目にも留まらず、こっそり戻ってきた。結局隣近所に兄達は避難したことになってしまった。
一緒に避難に出発した本家のミンイ兄さんも自分の家へ行って、兄達だけのうっとうしい隠遁生活が始まった。私達は十分な食料とゆとりある保存食糧を持っていた。
家は敷地が広いだけで、隣に新しく建った文化住宅に比べたら、取るに足りない古家で、隣近所では人情の厚い善良な隣人として知られていて、私達の生活は通りからあまりにも深く隠れていた。
ちょっとうっとうしく退屈なだけで、申し分のない良い条件の中で6.25を迎えて、変わった世の中を無事に静かに過ごしていた。
勿論、いきなり訪れる民請員たち、女性同盟員たちの目から兄達を保護するために、用意周到に隠れ場所を用意しておいた。
台所の板の間の天井は、納戸とは分離していても、天井がべニア板ではない頑丈な板になっていて、母と私は板の片側をはがして、その上にまんまと見事な部屋を整えた。
ラジオとギターと電気スタンドに本まで備えたのに、彼らはそこにじっと耐え忍ぶことができなかった。彼らは一日に何度も天井を上がったり下りたりした。戦争になったというので、少しもじっとしていることができない彼らの癖に、称賛に値するような変化が生まれるはずはまずなかった。
面白いニュースを聞いたと母に報告しに、間食の材料を探して求めて、煙草を吸いに、冷水に足を浸しに、彼らは忙しく上り下りして、彼らの溌剌とした若さは、その程度の運動をしなくては我慢できなかった。
母は兄達が前庭や裏庭をうろつくことを一番嫌がった。ソウルの家がいくら大きくても、近隣から完全に遮断されるはずがなかった。前庭では遠くからでも国民学校の屋上が見え、屋上にはよく軍服を身に着けた軍人がうろうろしているのが見えて、母はそれがあたかも家の庭を望んでいるようで、ぞっとした。裏庭は一度も戦地になったことのない伊吹やモミといった常緑樹と緑陰の濃いイチョウが濃い茂みをつくっており、昼間でもひっそりと清々しくて、蒸し暑い日だったら、ひょいと木の陰で昼寝を楽しむけれど、前庭よりは少し近くに近隣の洋館の窓が目に入った。
「あれまあ、そのまま上がりなさい。級長、上がれ」
母はまた毎日往来している人民班長を一番恐れた。男の履物はことごとく片付けて、ついに洗濯までも男の物は部屋の隅で乾かすなど、片時も安心できないのもすべて人民班長のせいだった。
すべての事がうまくいった。それに、世の中もうまくいくようだった。兄達は自分達が自由になる日も遠くないと早くからそわそわしていた。
「男の子が離れるべきなのか。国軍だけもう一度帰って来い。直ちに入隊してうっぷん晴らしを思う存分してやるよ」
- 続 -