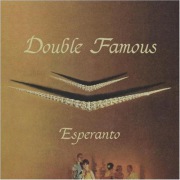1993年結成。もうすぐ結成20周年を迎えようとするDouble Famous、通称「無国籍音楽のエスペラント楽団」。青柳拓次や畠山美由紀等が在籍し、北海道のライジングサンからフジロック・フェスティバル、そして福岡のサンセットライブまでのフェス・ツアーを行ったり、恵比寿のガーデンホールを満杯にしたりしていた。京都にいた僕は、その馴染みやすいサウンドと青柳拓次等が持つスター性、そして今回フリー・ダウンロードで紹介するシリンダー録音音源を発表するような実験性に、憧れを抱き続けていた。下記の解説のように、2007年頃には、彼らはこんな楽しいことをしていたのだ。
そんな彼らも、2009年に青柳拓次や畠山美由紀等のスター性を持つコア・メンバーが脱退し、大きな転換期を迎えた。そこで彼らが選んだのは、「毎週火曜日に練習し続ける」こと。Double Famousの最も実験的な音源を聞きながら、そしてこのインタビューを読みながら彼らの軌跡を旅して欲しい。脱退や解散のニュースが飛び交う中、この記録は多くのバンドマンの指標になるだろう。音楽は人生と共に並走する。Double Famousは、そのことを示してくれている。
インタビュー : 飯田仁一郎(Limited Express (has gone?)) / 文 : 井上沙織
100年前と現代、ふたつの録音技術で比べるDouble Famousのサウンド
>>『Common Songs (Cylinder ver.)』のフリー・ダウンロードはこちら
左)『Common Songs (Cylinder ver.)』(シリンダー録音)
★FREE DOWNLOAD!
エジソンが発明した世界初の録音機ワックスシリンダー(蝋管)を使って録音された蓄音機バージョン音源。
『Common Songs (Cylinder ver.)』のフリー・ダウンロードはこちら
右) 『Common Songs(Silicon ver.)』(PCM録音)
まとめ購入 : 200円
デジタル機器を使って録音された現代の録音機バージョン音源。
この録音は、ダブル・フェイマスが2007年に行ったレコーディングの記録です。あの発明王エジソンが作ったはじめての録音機ワックスシリンダー(蝋管)を使って録音されたものです。100年前の録音機材を使って録音し、同じ演奏を100年後のハイテク機材でも同時に録音して聴き比べるという実験のような企画で、ある雑誌の100号記念の付録として配布されました。
いっさい電機も使わず、ゼンマイで動くコップのような形をしたワックスシリンダー(蝋管)に直接書きこんでいくこの録音方法だと実際の楽器の演奏をその場で耳で聴くのとは全く違った音像になりますが、すべての録音芸術の原点である人類が初めて聴いた過去の音は、こんな姿をしていたのです。この機械がエジソンによって発明されたほんの100年ほど前まで、人類はこだま以外の過去の音を聴くことはできませんでした。音を記録してまた再生できたというだけでもう魔法を見るように驚いてた時代のものだから、その驚きや喜びが伝わるような気がします。
この3曲は実際にエジソンが生きていた時代に演奏されていて、現在ではすでに著作権の消滅したパブリック・ドメインの楽曲です。ワックスシリンダーは2分までしか録音できないため、すべて2分以内に収まるようにダブル・フェイマスがオリジナルアレンジをほどこしました。ダビングなども一切できないため、ワンテイク一発録りで録音され、まちがえたり音が外れたりしたものもそのまま収録しています。(text by 坂口修一郎(Double Famous))
幻の1stアルバム、リマスタリング版販売開始!
1998年にリリースされ、今では入手困難な幻の1stアルバムのリマスタリング版。現在でもライブのハイライトで演奏される初期の代表曲「Jump Up」「Africa」を含む全15曲を収録。
【トラックリスト】
1. Mandrill / 2. Kananaski Moon / 3. Kakio / 4. Interlude / 5. Jump Up / 6. Getting Fat Blue / 7. Zeze / 8. Serenade / 9. Conga Habanera / 10. Aging Care / 11. Desapareca, Va, Desapareca / 12. Orca / 13. Nocturne / 14. Africa / 15. Dodo Titit Maman
Double Famous 坂口修一郎(Tr./Tb./Per.) インタビュー
ーー青柳(拓次)さんが抜けた2009年、バンドはどのような状況だったのでしょうか。
坂口修一郎(Double Famous) : まず、ダブル・フェイマスって、必要な時だけ集まってちょっとリハーサルやって本番みたいな、いわゆるプロのミュージシャン・シップがあるバンドじゃないんです。街の青年団みたいに「毎週火曜日に集まって練習する」っていうのを学生の頃から15年位ずっと続けていて、その練習がダブル・フェイマスを形作る骨格になっている。そんな中で、僕らもそのころ30代半ばを過ぎて、それぞれの生活や人生のいろんなことがある中で、青柳も結婚して子供も生まれて、「東京にはあまり魅力を感じていない。できれば住みやすいところに移住して子供を育てたい」というようなことを言っていたんですね。その後彼は、一回活動を整理して沖縄に行くと決めたので、物理的に練習に参加するのが難しいなら、バンドのコア・メンバーとしては一度離れるという話になりました。

それ以前にダブル・フェイマスは、2002年あたりから「音楽だけで食っていく」という考えを捨てるという話をしていたんですよ。2001年に2ndアルバム『Souvenir』のリリースがあって、その年のフジロックにも出させてもらったりして、僕らとしてはある程度お金に対する期待があったんです。もう少し楽に活動出来るようになるんじゃないかと。でも2000年頃から色々やっていたものの、思っていた程甘くなかった。2005年には、自分達で原盤権を持ってリリースしたんですけど、実際出してみると、やっぱりレコード会社もビジネスなので、自分達で原盤権を持っていない作品だと告知や宣伝の量も減ったり。世の中の流れもあって売れる枚数もどんどん減っていって。
ーー2002年頃って、レコード・バブルのときじゃないですか。野音やO-EASTでやっていたバンドが食えていなかったって、結構センセーショナルな話ですね。
バンドの活動自体はどんどん派手になっていったんですけどね。ステージも大きくなっていったし、畠山(美由紀)はソロでデビューしたし、トピックはたくさんあった。『Souvenir』のレコ発は、横浜中華街の同發(どうはつ)っていうレストランを借しきって、お客さんを全部招待して、ディナーショー形式でやったんですよ。
ーーディナーショーなのに招待なんですか?!
そう(笑)。お客さんからお金を貰うことができなかったので、次のアルバムの制作費とかを捻出して社内でやりくりしてくれたようです。とにかく面白いことをやりたかったんですよ。「昔、細野さんがティン・パン・アレイでやったことがある横浜のレストランがあるらしいから、探しに行ってみよう! 」って自分達でロケハンしに行って。当日は、僕らが一人2曲ずつ選んだミックス・テープをお客さんにプレゼントしたんです。とにかく「こんなことできたら面白いよね」っていうことをやれていたんですよね。その後、2003年にライブ盤『Live in Japan』を出したんですけど、その時も湯島聖堂を全部借りてライヴをやりました。やりがいも手応えもあったんだけど、一連のプロジェクトが終わってみると、「え、こんなに色々やってきたのに、残ったお金ってこれだけ?! 」となったんですよね。一年間やって、とてもダブル・フェイマス10人が食える額ではなかった。

ーー当時はアルバイトをしながら活動をされていたんでしょうか?
当時僕はアパレルのブランドで働いていたんだけど、あまりにもダブル・フェイマスの活動が忙しくなっちゃったので、一回辞めたんです。それからは派遣で働いたり、フリーランスで他の人の作品にミュージシャンとして参加したりしていました。でもあまりにも収入のアップダウンが激しくて、曲作りしようにも集中できなかった時期もありましたね。その頃は『Live in Japan』が一瞬オリコン・チャートにも入ったりしていて、セールスもそれなりにはあったんですけど厳しかった。僕、CDの流通の会社でも仕事していたことがあるんですけど、流通の世界でダブル・フェイマスをみたら、それなりに知名度が上がっていても、売上が全くついてきていなかったんですね。けっして売れて無くはないんだけど、さらにもうひとつ上にいかないと、売上が10万枚は超えていかないと10人で普通に食っていくのは難しいんじゃないかと。でもそんなリリースを毎年続けていくのは無理だろうし、その時点で結成してから10年位経っていたので、これはどう計算しても食えるようにならないから、考え方を変えた方がいいんじゃないかなって思いはじめたんです。ちょうどその頃にCCCDの問題も出てきたりして、このままいったら活動を続けることも出来なくなるんじゃないの? って、もの凄く危機感を持っていた時期でもありましたね。
ーー他のメンバーはどのように考えていたのでしょう?
どうすればいいのかは一人一人が考えて、皆フリーランスで仕事をするようになっていきました。音楽専業のメンバーもいたけど、ライターやったりグラフィック・デザインやったり。それで収入を得つつ、音楽活動の時間を取れるような体制を自分達で作っていった。それができているから続けていられるんですよね。あとは、個々の道を歩み出したメンバーもいます。畠山は音楽だけで食っていこうと決意していたので、一度離れて、出来るときがきたらまた一緒にやろうよって話をしました。
ーーダブル・フェイマスのリーダーは坂口さんなのでしょうか?
いや、ダブル・フェイマスはリーダーが居ないんです。僕はリーダーというよりも営業担当ですね。皆が等しく意見を言うようにしていますけど、外に出て行くスポークスマンだったりレコード会社との契約のときに前に立ったりするのはだいたいは僕がやっています。僕がそういうの向きというか、契約したり話をまとめたり、スキームを作ったりするのが好きなんですよね。「どうにかして続けるやり方を考えよう、それでいて面白いことを考えよう」って、常に考えています。

きちんと波を作ってから、身の丈に戻す
ーー音楽で食べていかないと決めてからは、どのように活動してきたのでしょうか。
火曜日の練習を続けられるように、それぞれがシフトしていきましたね。ライブがあるから集まるようにしていると「忙しいから参加できない」ってなっちゃうので、火曜の夜は空けるって決めて、予定がなくてもその日は集まるようにしました。練習しないで喋っているだけのときもあったりします。プロジェクトとしてやっているとその度に招集をかけなければいけないので、そうではなくて、自分達の生活のルーティーンに入れてしまおうと。
ーー転機はありましたか?
2009年に活動の仕方を変えました。2008年にアルバム『DOUBLE FAMOUS』を出したんですけど、メンバーが皆30代後半に差し掛かってきたのと同様に、お客さんも年を重ねていて、このままいくと若い子が聴いてくれなくなるなって思ったんですよね。ヒット曲があればまだしも、僕らはヒット曲が出るようなバンドじゃないんで、ここで一回「こういうバンドがいるよ」って提示しておかないと、その後の活動が限られた範囲のものになってしまうと思ったんですよね。
ーーなるほど。
それで、2008年にフェス・ツアーをやりました。フジロックをはじめ札幌のライジングサンから福岡のサンセットまで、十何箇所、フェスだけを回った。そして一番最後にワンマンを恵比寿のガーデンホールやりました。このツアーは元々2006年頃から考えはじめていて、「バンド結成15周年の2008年にアルバムを出すから、その時にイベントに出してほしい」って各地のイベンターにアプローチしていたんです。それで「これだけフェス出演を決めてきました」って、エイベックスにアルバムの話を持っていって、『DOUBLE FAMOUS』を出したんです。その一連の流れをひとつの山にして、そこから先はマイペースに、まずは身の丈でできることをやっていくことにしようと考えていました。

ーー大掛かりなプロジェクトですよね。フェス・ツアー、よく組みましたね!
3年かけてやっていました。その時にTONEの是澤さんに「一年間だけ事務所に入れてほしい」と頭を下げに行ったんです。ブッキングとかは自分達でもやるんだけど、個人だと契約はしづらいので、それをTONEで受けてもらえないかと。フェスをまわるにあたっても、基本僕が中心に動いてはいたんですけど、TONEの人間としてやるっていう仕組みにして。もちろん是澤さんにもバックアップしてもらって、最終的にガーデンホールでのライヴは、ビデオも撮ってP-VINEから出しました。青柳にもそのライヴまでは居てもらって。せっかく学生の頃からずっとやってきたし、15年の節目までは一緒にやろうって話していたんです。なんとなくフェイドアウトしていくのは嫌だったんですよね。身の丈に戻すのはいいんだけど、きちんと波を作ってからにしようと。それ以降は自分達が本当にやりたいことや、地方のオーガナイザーのところに行くとか、面白いと思えることだけやっていくことにしたんです。
ーーそして、2009年にガーデンホールを埋めて、青柳さん達が抜けました。そこからの3年はどのような変化がありましたか?
バンド初期の頃は、青柳と栗原が音楽監督/僕が営業担当って感じだったんですね。青柳とドラムの栗原は10代の頃にイカ天でデビューしているんですよ。彼らは高校を出たばかりの頃に自分の力で世に出ていて、音楽的に存在は大きかった。意見は皆フラットにしようって言っていたし、彼らも意見を聞く人だったんだけど、どうしても彼らの意見が際立ちすぎてフラットではなかったと思います。でも青柳が居なくなったことで、皆が彼に頼っていた部分が大きかったことがわかって。あ、自分達でやらなきゃ駄目なんだって思いはじめて、役割分担を明確にするようになったんです。それまで僕がずっとやっていたブッキングとかも分担して、アレンジにしても等しく意見が出てくるようになったりして。よくも悪くも、ダブル・フェイマス=青柳拓次と語られることが多かった。もしくはリトルクリーチャーズの別プロジェクトとかね。そうじゃなくて、ダブル・フェイマスはダブル・フェイマスだったので、そういう意味でも身の丈に戻ったんじゃないかな。有名な誰かが居るバンドじゃなくて、街のバンド・ダブル・フェイマス。
ーーその中でも活動スタンスは変わりませんか?
今でも火曜日に集まって練習しています。そろそろ40歳を過ぎて、それぞれ責任の大きい仕事をするようになってきたから、隔週になったりもするけど。それでも集まろうと。それだけがルールですね。周りにいろんなバンドがいたけど、90年代に活動を始めたバンドで何かしらの仕組みを作れなかった人達はここ数年で活動出来なくなっていっていますね。仕事も家族もあるし、どうしてもそっちが優先になってしまいますから。
ーー仕組みっていうのは、どうやって仕事と両立させるかということですよね。
うん、そうですね。やっぱり食っていかないといけないし、生活していく上で固定費はかかるわけじゃないですか。贅沢はしないとしても、自分達の創作活動を続けていく為のベースをどうやって作るのか。昔は、時間が自由になるフレキシブルなバイトをしながら音楽活動をやっている人がたくさんいた。でも、それっていつかは音楽で食っていくことを前提にしているんですよね。そのままのペースで活動を続けていくと、どんどん生活は苦しくなっていくし、給料を上げる為にはたくさん働かなきゃいけないけど、たくさん働くと活動の時間をとれなくなる。そういうジレンマに絶対30代で陥るんですよ。そうなると続かない。そうならないためには、時間給で働くのを辞める必要がある。ライターだったりグラフィック・デザインだったり、自分のもうひとつのスキルで稼いで、時間をつくる。やっぱりしんどくなったら続かないですよ。

ーー今、新たなダブル・フェイマスの形が確立しつつあると思うんですけど、それでもモチベーションを保ち続けるのはヘビーじゃないでしょうか?
まだ完全にうまく回っているとは思っていないけど、それぞれ別の仕事をしているので、ダブル・フェイマスを広告塔にして仕事に繋げたりしています。ジャケットやライナーノーツの編集もメンバーが手掛けているから、それを実績として別の仕事をとってきたり。コーヒー屋をやっているメンバーは、「ダブル・フェイマス・ブレンド」のコーヒーを作ったりしてね(笑)。僕は企画をするのが仕事なので、仕事とバンドが直接結びついたりすることはなかなかないけど、こうやってダブル・フェイマスの活動をすることで、裏の人と交渉したりするので、そこから別の仕事に繋がっていったりしますしね。
ーーサウンドはどうですか? 青柳さん達が抜けて、新しい音は確立されてきましたか?
単純に、メンバーが減って10あった楽器が7になったので、音の数は減りました。それを変に増やそうとしたり、ゲストを呼んだりせずに、無いものは無いと考えて、目の前にある素材だけでやっていこうと話しあって決めてやっています。そうするとアレンジも変わらざるを得ないし、今までにやってきたことの焼き直しでもなく、同じ曲でも編成が違うことで全然別ものになっています。それも、身の丈でやろうっていうスタンスですね。昔よりもペースは落ちているけど、新曲もどんどん作ってますよ。
ーー未来はどう考えていますか? この5年はダブル・フェイマスをどう作っていきたいのでしょう。
今年、来年辺りは今の活動ペースでやっていくと思います。もっと先、5年~10年先の話をするなら、僕は50、60歳になっても続けていきたいと思っているんですよ。メンバーの子供もどんどん増えていくし、地方に行ったメンバーもいるし、僕自身も今は地元の鹿児島に頻繁に帰って向こうでも活動していたりする。更にマイペースな活動にならざるを得ないと思うけど、物理的な距離はバラバラでも活動できるといいなと思っています。今は未だ難しくても、インターネットや交通のインフラもどんどん整っていくだろうし。毎週火曜日にスタジオに集まるのは無理かもしれないけど、曲のファイルを送りあって皆でアレンジだけは決めて活動するとかね。時代に合った活動の仕方をしていければいいなと思っています。海外にいるメンバーがいてもいいかもしれないですしね。
ーーそれって現実的に可能なんでしょうか?
以前キャレキシコが日本にきたときに、2、3回一緒にツアーを回ったんですよ。彼らはアメリカのトゥーソンというもの凄い田舎に住んでいるんですけど、他のメンバーはアリゾナにいたり、メンフィスにいたり、ヨーロッパにいたりするんです。彼らは、何処かで落ち合ってツアーに出るんです。ヨーロッパでやるときは、例えばドイツのベルリンで落ち合ってリハ―サルをやってツアーに出る。そういう生活をしているんです。「皆住んでいるところが近くじゃなくてもやれるんだね」って聞いたら「自分達の住んでいる街が好きだし離れるつもりもないし、大都市に集合して大変な思いをして狭いところでやるよりは、それぞれが自分達のスタジオを持っているから楽譜や音源のやりとりで充分やれている」って言っていたんです。あの広いアメリカとヨーロッパでそれができるなら日本でも出来るんじゃないかと(笑)。あんな風にできたらいいよね、っていうのがイメージとしてあるんですよね。
ーー本当にそれができたらすごいですよね。
僕が鹿児島から出てきたのが18歳のときで、その頃は音楽の情報を得るには雑誌かラジオしかなかったんですよね。だから活動する為には東京に出てくるしかないと思っていたし、そういう人が多かったと思うんだけど、今後は自分の地元でも充分活動していける。そこから直接他の地域の人とインターネットを介して音源のやりとりをして、モノが出来たらどこかで落ち合ってセッションする、っていうことができるようになるといいなと思うんです。僕個人的には5年以内にはダブル・フェイマスもそういうふうにしたいですね。そうすれば地方に移住した連中もまた戻ってきたりするかもしれない。子供も増えているからメンバーが増えるかもしれないけど(笑)。

ーーダブル・フェイマスの未来を作る上で、「止める」っていう選択肢もあるじゃないですか。それをしないのは確固たる何かがあるのでしょうか?
止めるのはいつでもできますけど、続けるのは続けていないとできないじゃないですか。ダブル・フェイマスは今年19年目なんですけど、19年やり続けたから今があると思うんですよ。仮に、ダブル・フェイマスがやっていることを譜面に起こしてスタジオ・ミュージシャンに渡したら、「せーの」で簡単に出来ちゃうと思うんですけど、音楽は絶対に同じにならない。19年一緒にやってきたからこそわかる、メンバーそれぞれの人間性が滲み出ているんですよね。積み上げてきたものを壊すのは、ポンと一発叩けばできるけど、それはもったいない。今は離れたメンバーも帰ってくる家がなければただ離散して終わりで、「ああ、そういえばそんなバンドあったね」で終わっちゃうと思うんですよね。それはあまりにも惜しいですよ。そう自分が思っている限りは続けると思いますね。
Double Famous PROFILE
1993年結成。友人たちと主宰したイベント "Brilliant Colors"(下北沢Zoo/Slitz)での月1のライブをベースとして、ゆるやかに活動を開始。遠く離れた島や大陸、山峡や街角の音楽を自分たちの暮らす土地へと引き寄せ、その時々にメンバーたちがむさぼり食べていた諸々雑多な音楽とともに消化させ紡ぎ出された音楽は、東京発のエキゾチック・ミュージックと呼ばれるようになり、ダンスホール楽団として日本各地を気の向くままに訪れる。『esperanto』から『Doubele Famous』まで、現在までに5枚のオリジナル・アルバムを発表。結成15周年の全国ツアーを終えた2009年、青柳拓次(g,acc)が脱退、栗林 慧 (uku)、民 (per)、畠山 美由紀 (vo)が休止するも、新メンバーに藤堂正寛(key)を加えて、あいかわらずマイペースに活動中。これまでとはひと味違った野性味あふれるかっこよさです。。